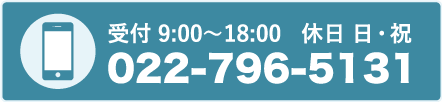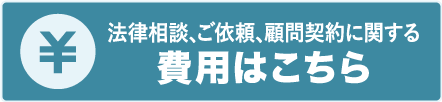相手方と話し合いが進まない場合、調停手続きを勧められる場合があります。
特に弁護士に相談に行き、経緯や証拠関係など、詳細をお話しした結果、弁護士から調停をしたらどうかと言われる場合がよくあります。
また、インターネットなどで、こういう場合は調停が良いという記事を見るなどして、調停が視野に入ることもあるでしょう。
とはいえ、具体的にイメージがつかず、悩んでしまう人もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は、調停とはどのような制度か(調停が利用できる場合や手続き)についてお話ししたいと思います。
調停とは
調停とは、裁判所(簡易裁判所、家庭裁判所)で行う手続きで、間に調停委員という第三者が入り、当事者間の話し合いを促進してくれる制度です。
調停を裁判所に申し込むと、後日、双方呼び出しがあり、裁判所に赴いて(場合によっては電話などで出席して)双方が調停委員を介して話し合いを行います。
一般的には、当事者双方面と向かって話すというよりは、双方が調停委員にそれぞれ話す(話さない方が控え室で待機する)という形で進むことが多いです。
調停に向いている紛争
親族間や友人間など、裁判を行うまでではない場合、調停による話し合いが向いています。
また、証拠が一部不足していたり、かなり細かい経緯が関係したりなど、裁判が向いていない場合に調停の方が良いこともあります。
離婚などは裁判の前に調停を行う必要がありますし、養育費などや相続なども調停から審判に移行することが多いため、このような場合も調停が向いています。
逆に相手の居所が分からない、相手と連絡が取れないなどの場合には調停は向いていません。
手続きはどうすれば良いか
調停は弁護士に依頼すれば弁護士の方で手続きを行ってくれますが、自分でも申立てることは比較的簡単です。
具体的には裁判所に申立書と必要書類(印紙や切手も含む)を提出すれば良いのですが、裁判所で手続きについて聞くこともできます。
また、調停が開始した以降も、話し合いがベースですので、それほど難しくはないことも多いです。